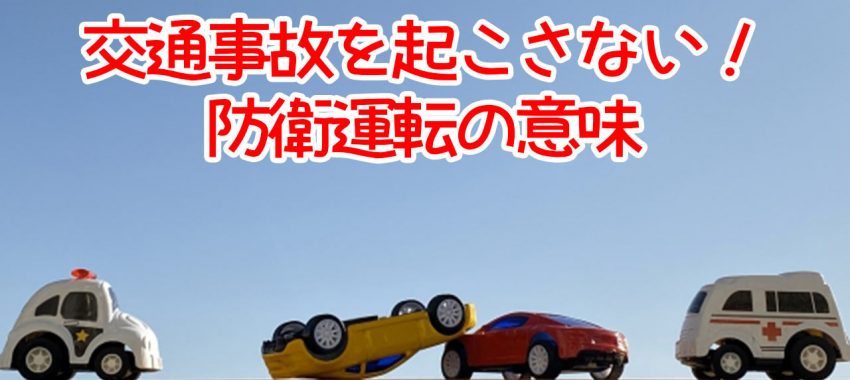Author: tamai03
大雨で車が冠水したら
大雨が降ったら冠水する場所には近寄らない

館林も雨が降ると冠水しやすい場所がいくつもあります。
運転していると、大雨に遭遇する可能性がありますが、その時にどのような行動をとるのかが大きなカギを握るのです。
館林周辺の道路では、新宿のアンダーパスは冠水することでよく知られています。
他にも新しくできた道路ですが、東武鉄道のアンダーパス、ベルクの横にあるところも冠水しやすい傾向があるのです。
運転しているときにこのような場所に差し掛かったらどうなるでしょう。
冠水することが予想される場所には、大雨が降ったら近寄らないことが大切です。
水をかぶればエンジンが止まり動けなくなる

もしも、冠水したら、車から脱出する方法を考えなければいけません。
冠水した状態では、この後怪我では済まない状況が予想されます。
まず外側からかかる水圧によって扉は開かなくなります。
扉が開かないのですから脱出できないことになるのです。
簡単に開くと思うかもしれませんが、水圧も力は強く人間が落ち返せるようなものではありません。
さらにマフラーより高い位置まで水が来れば、エンジンの中に吸い込まれる可能性が出てきます。
マニュアル車であればクラッチを切った瞬間に水が浸入してきますし、オートマ車でも吸い込まれていく可能性があるのです。
仮に吸い込まれなかったとしても、エンジンの高さまで冠水すればバッテリーが耐えられません。
エンジンが止まれば現在の車は窓も開かない状態です。
脱出できなくなる可能性が更に高まります。
車は水位が車の底面まで来ると、押し上げる力が働きます。
路面から離れていくような感覚がしているのも、この力が働いているからです。
こうなるとエンジンがかかっていたとしても、車は動くことが出来ません。
できるだけ早く外へ出られる方法を考える必要があるのです。
ヘッドレストで窓を割る

扉が開かない状況であれば、エンジンが止まる前に窓を開けます。
力いっぱい押し下げることで、窓を開くことができるでしょう。
もしも、その前にバッテリーが止まってしまったら、シートにあるヘッドレストを抜き取ります。
現在のヘッドレストは2本の支柱で支えられており、抜き取ると先端部分が尖っていることがわかるでしょう。
車の窓ガラスは簡単に割れないように作られていますが、衝撃を点で与えることにより、破ることができるのです。
もちろん、割った時に怪我する可能性はありますが、これで脱出の経路が確保できるのは覚えておくべきでしょう。
一番大事なことは、冠水する場所には近寄らないことです。
興味本位で車を乗り入れた瞬間に、浮き上がってしまい身動きが取れないことも考えられます。
気がついたときには手遅れとなるため、大雨が降ったら注意して走りましょう。
交通事故でドライバーに発生する3つの責任
ドライバーが問われる刑事責任

交通事故を起こした加害者が身勝手なことを言うのはよくあるケースです。
しかし、ドライバーとしては責任は問われるのは当然であり、非常に重いケースも出てきます。
一般的な例の交通事故ってどのような責任に問われるのか考えてみる必要があるでしょう。
交差点で歩行者と接触した交通事故で相手に怪我をさせたと設定してみます。
相手を怪我させたという事実がここにありますが、そこで問われるのが自動車運転過失致傷罪です。
つまり、車を運転したことで交通事故を起こし相手を怪我させてしまったという罪に問われます。
操作の対象にもなりますし裁判によって刑罰を科せられる可能性が高いでしょう。
もちろん、怪我の内容によっても問われる罪の大きさに違いが出てきます。
どのような運転をしていたかによっても違いますが、これが刑事上の責任です。
もしも、死亡事故のような状況であったとすれば、実刑判決がつくことが考えられます。
交通刑務所へ行くことが考えられる状況です。
さらに飲酒運転であればもっと厳しい判決が待っています。
被害者の損害賠償

歩行者が怪我をした事実から、治療を受けることも考えられるでしょう。
入院するケースも出てきます。
入院すれば当然仕事には行けなくなり、そのぶん会社を休まなければいけません。
当然収入が減少することになり損害賠償の請求が発生します。
歩行者側に問題があったケースも考えられます。
本来は歩道を歩いていなければいけませんが、車道や横断歩道外を利用していた場合には歩行者側にも責任が出てくるのです。
この場合には責任の相殺をします。
過失相殺と呼ばれますが、お互いの過失を相殺し損害賠償金を減額するのです。
損害賠償の責任は非常に重くのしかかるため、保険に加入することが必須といえます。
交通事故では、自分の経済能力では支払えない請求が降って湧いてくる可能性が高いのです。
運転免許の点数

交通事故を起こすと運転免許の点数が引かれます。
事故の内容や状況、その後の行動などで判断され、免許停止か取消しの処分もあるのはドライバーなら知っているでしょう。
しばらく運転できないだけではなく、免許の再取得にも制限がかかります。
講習を受けることで期間を短縮したりもできますが、これは行政上の責任として問われている部分です。
これらの責任を見て分かる通り、それぞれが問われている内容に違いがあります。
ハンドルを握るドライバーはこれらの責任を持って運転していなければいけないのです。
ただし、交通事故の内容によっては、民事的な責任は問われても刑事的責任は問われないケースもあります。
手続きはそれぞれが別になるため起こるケースですが、ドライバーは責任を持って運転しなければいけません。
左折で左側を開ける運転は危険です
左側を空ける大きなリスク

館林のスーパーなどで見かけることがある危険な行動として、左折するのに左側を空けている人を見かけませんか。
実は非常に安全意識の低い運転であり、防衛運転としても大きな問題を抱えています。
左折する際には巻き込みの危険性があるのは誰でも分かるはずです。
これがわからないドライバーはそもそも適性に問題があると言えます。
なぜ左側を開けてはいけないのでしょうか。
もしここに隙間があることに気がついた自転車がいて、そこを通り抜けようと思ったら危険だと思いませんか。
その自転車に気付かず車が左折すれば巻き込んでしまいます。
この隙間が空いていなければ自転車はその意識を持ちません。
歩行者も同じです。
教習所でも左折させてる時には左側にスペースを空けないと習うでしょう。
なぜならば隙間があれば入ってこようと考えるからです。
この危険予測ができていないからこそ、スーパーの出入口などで左側が空いています。
このような安全意識に対するレベルの低さは危機管理能力の低さとも言えるでしょう。
ハンドルを握る以上防衛運転は絶対に必要です。
その知識を持たないだけでも危険な状態にあることに気がつかなければいけません。
大回りしなければ曲がれない勘違い

左側を開けている理由の一つに、大回りしなければ曲がれないと勘違いしているドライバーがいます。
トラックが左側を開けて大回りをするのを見て、自分の車もそうしたら楽ではないかと考えるところから始まっているのです。
しかし、そもそも車の条件が違います。
トラックなどをホイールベースの長い車は、内輪差が大きくなります。
この内輪差をカバーするためには大回りしなければいけません。
車の前方部をできるだけ前に出してからハンドルをゆっくり行って曲がっていくのです。
一般の乗用車でこの動作が必要かと言われれば、ほぼ必要ありません。
一般の乗用車は最小回転半径が小さく、ホイールベースもトラックに比べれば遥かに短い車です。
このような車が大回りして曲がる必要性はほぼありません。

大回りして曲がるということはそれだけハンドルを切らなければいけません。
ハンドルを切る量が多くなればそれだけ注意が向いてしまいます。
何かあった時に停める動作も必要です。
つまり、それだけ危険があった時に対処できなくなるのです。
この状況を理解しているドライバーがどれほどいるでしょうか。
実際に大回りしているドライバーにはこのような危険意識はありません。
自分が曲がるのに楽ができると勘違いしているだけで、非常に危険な行動なのを理解していないのです。
大回りすればそれだけ視界も失われやすくなります。
みなければ安全とは言えない情報も増えていくのです。
それだけ運転も難しくなることを理解すれば、出口で左折しなければいけない時にどのような運転にするべきなのかすぐに分かるでしょう。
これがわからないドライバーは防衛運転ができない人であり、免許を返納するべきと言われても致し方ないレベルなのです。
強い方かもしれませんが、車は人と接触すれば怪我をさせてしまいます。
大きな交通事故につながる前に運転を理解し直す努力が必要です。
客観的な証拠となる交通事故の写真
事故現場の写真

交通事故にあってしまうのは不幸なことです。
その時にどのような状況だったのか、はっきりと伝えられる状況を作らなければいけません。
そのためにどのようなことをしたらいいのか、知識を持つことが必要です。
損害賠償の請求をするとしても、交通事故の状況を説明できる状況を作る必要が出てきます。
客観的な証拠の提示が必要となりますが、最も有効なのは写真です。
つまり、交通事故にあったときには、できるだけ写真を撮らなければいけません。
現在ではスマートフォンの普及により、多くの人がすぐに写真が撮れる状況にあります。
交通事故の直後は気が動転しているものではありますが、状況を客観的に説明するためには有効な手段であることを覚えておかなければいけません。
全体を俯瞰できるように

交通事故の写真の有効性が出てくるのはセンターラインオーバーの場合です。
センターラインをオーバーして突っ込まれた場合などでは、それを証明するのが非常に難しい状況が生まれます。
車両の損傷状況からどちらがオーバーしたのか判断するのは容易なことではないのです。
この時に客観的に状況を説明できる写真があると、とてもスムーズに状況判断につながります。
客観的な情報を用意することにより、後々揉めないで済むことも重要なポイントになります。
写真を撮る際には、全体的に俯瞰できる情報が必要です。
事故直後にどのような車の位置になったのか、わかるようにします。
これだけでも交通事故の状況を客観的に判断できるからです。
路面の状況も

路面の状況写真も必要です。
タイヤ痕などは、雨ですぐに消えてきまいます。
時間がたつと分からなくなるため、写真が客観的な証拠になるのです。
それも当日、その時間に撮ったところに意味があります。
ほかの情報が混ざらないようにすることによって、証拠としての価値が上がるのです。
このような写真は警察も保険会社も撮影します。
しかし、その場にいない以上、時間がたってから写真を撮るため、どうしても状況が変わるのです。
これでは客観的な証明に役立てられない可能性が出てきます。
自分で自分を守るという意味でも、手軽に撮れる方法でも残しておかなければいけないのです。
もちろん、怪我などをしていれば、この限りではありません。
人命救助が最優先事項であり、自分が怪我をしているのに写真を撮って悪化させる意味はないからです。
それでも、このような客観的な証拠が重要となることは覚えておきましょう。
交通事故は警察へ通報すること
当事者同士の話し合いは危険

交通事故にあったら、警察に通報することです。
もちろん、安全の確保など重要なことは先に行わなければいけません。
けが人の救助なども大切です。
その中の条件の一つとして警察に通報することを忘れてはいけません。
特に軽い物損事故の場合、警察を呼ぶかどうか判断を迷う可能性があります
しかし、当事者同士の話し合いだけで解決しようとすると、後で後悔するかもしれないのです。
道路交通法でも決められている

当事者同士で話し合いをして解決しようとすると、解決したつもりになります。
ですが、実はお互いが納得していない状況も生まれてくるのです。
約束として口頭でも成立はしますが、後から多額の修理費を請求されるようなこともあるかもしれません。
治療費が膨大な金額になる可能性も出てきます。
このような状況の中で当事者同士だけで話し合っていると、うまく問題を解決できないかもしれないのです。
実は道路交通法の中でも警察に通報しなければいけないとしています。
これは義務付けであり、通報をしなかった場合には3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられるのです。
道路交通法第19条に乗っていますが、知らなかったでは済まされないでしょう。
交通事故証明書を発行してもらう

もう一つ重要なポイントが事故による修理費の請求に関わってきます。
修理票を請求する場合には保険会社から交通事故証明書を発行してもらうように指示されるはずです。
これは警察が作成するものであり、他の個人が作るものではありません。
交通事故を通報していなければ、交通事故が起きたことを認識していない状態となり、交通事故証明書は発行されないのです。
大きな交通事故があったとしても、それは事実として認定されない可能性が出てきます。
特に保険の場合には、この状況が非常に大きく左右するのです。
警察に通報する必要があるのは、交通事故の被害の大小に影響されません。
もしかしたら、軽くぶつかっただけでも、数時間後に体が痛み出し、治療を受けなければいけないかもしれないでしょう。
ひどいケースでは、数時間後になくなってしまうような場合さえあります。
加害者側では大したことがないと思っていても、被害を受けた側では実は大きなダメージが残ったりするのです。
当事者同士の安易な話し合いで済まそうとするのは簡単ですが、後の被害状況を考えると非常に大きな問題となるのを忘れないようにしましょう。
もちろん加害者の場合でも同じです。
後で補償などでもめる可能性を少なくするためにも、交通事故の発生後に必ず警察を入れましょう。
安全運転は確認からの情報が必須
車を安全に運転することと確認

車の運転で大切なことは何かと言われれば、安全の確認以上のことはありません。
自分が安全であるかどうか確認し、安全な運転を心がけることにより、交通事故の可能性を下げられます。
もちろん全てゼロになるとは限りません。
ですが少しでも安全な運転を心がけるためには、確認という行動が欠かせないのです。
なぜ確認が必要なのか改めて考えてみる必要があるでしょう。
情報がすべて

我々が車を運転するときに大切なことは情報を得ることです。
今目の前に車が走っているかどうか、対向車が来るかどうかは全て情報です。
歩行者が見えていたりすることもあるでしょう。
もしかしたら止まっている車が目の前にあり、その陰に子供がいる気配がするかもしれません。
これも全て情報なのです。
仮にこの情報がなかったと仮定しましょう。
対向車が来るかどうかわからないところで車線をはみ出して走ったらどうなるか、ドライバーであればすぐに分かるはずです。
かわすことができなければ正面衝突する交通事故になります。
歩行者がいることに気がつかず左折したらどうなるでしょうか。
その歩行者を巻き込み人身事故を起こす可能性が高いはずです。
目の前の車が急ブレーキを踏んだことに気がつかなければ追突するかもしれません。
全ては状況がわかれば回避できる部分があります。
どれもすべて情報が大切になるのです。
状況を判断するためには全て情報から判別していかなければいけないのが車の運転なのを忘れてはいけません。
確認をする行動の意味

情報を得るためには確認が必要です。
例えばバックミラーやサイドミラー、アンダーミラーなどを見て問題がないか確認する行動はドライバーなら必ずします。
前を見て運転するだけではありません。
自分の左右や後ろに何か問題があるかどうか、他の情報も加味しながら運転するのです。
つまり確認ができている人ほど安全な運転に近づくと言えるでしょう。
逆に情報を得られない人は常に危険と隣り合わせになります。
それがドライバーだけであれば構いません。
自己責任になるからです。
ところが交通事故には、他の人を巻き込む可能性が出てきます。
自分だけでは済まないのです。
初心者の若葉マークであろうとも、路上に出れば一人のドライバーとして同じ扱いになります。
交通事故を起こした時に初心者だから許されることはありません。
経験が少ないから人をひいても許されることなどありえる話ではないでしょう。
だからこそ常に安全かどうか確認し運転しなければいけません。
いかに安全かどうか確認できる癖をつけることが、どんなドライバーにでも求められる条件になるのです。
忘れてはいけません。
事故を起こせば様々な人の運命を狂わせます。
自分の運命を狂わせるだけではなく、被害者の運命も変わってしまう状況を理解して運転しましょう。
防衛運転の鉄則とは
ドライバーが持たなければいけない防衛運転

防衛運転を心がけている人は非常に多くなってきました。
本来言葉にしないでも、ドライバーが意識していかなければいけない部分です。
その防衛運転の中には心がけなければいけない鉄則がいくつもあります。
改めて自分が守れているかどうか、これから先も心がけなければいけない部分として認識し直す必要があるでしょう。
子供はバスやタクシーなどの影からは飛び出してくると考える

防衛運転では子供に注意するのが最初のポイントです。
子供は大人が想像している行動とは異なる場合がよくあります。
車がきているのに飛び出す可能性があるのもその行動の一つでしょう。
常に子供が飛び出すかもしれないという考えを持てば、安全運転に繋がるのは確かです。
道路に親子を見つけた時には、速度を落とし徐行するのが基本です。
特に道路を挟んで両側にいるのを見かけた時には子供が親の方向へ飛び出すかもしれません。
もちろん、子供が危険だと考えていればこのような行動は起こしませんが、車がいることを視野に入れていない可能性もあるのです。
飛び出すかもしれないと分かっていればこちらも準備ができます。
ブレーキも組めるようにしながら、すぐに停車できる速度に落とすことが防衛運転として大切です。
バスやタクシーが停車している時も危険があると考えなければいけません。
利用者はそれらの交通機関から降りてくるのです。
危険があると思って降りる人もいますが、車に気がつかない場合もあるでしょう。
交通事故に繋がる非常に危険な状況となるため、防衛運転が必要となるのです。
ドライバーとしての注意も大切

自転車を見かけた時にも注意が必要です。
自転車が急に曲がるかもしれませんし、倒れてくるかもしれません。
高齢者の方が突然飛び降りて止まってしまう状況を見たことがあるでしょう。
速度を落としてすれ違うと思っていたのに、突然飛び降りられてしまうと減速が間に合わない可能性もあるのです。
自転車は危険なものだと考え感覚を取って走ることが防衛運転につながります。
左折時には巻き込み事故を起こさないように注意します。
日本の車は右ハンドルが基本で左側通行です。
左側はどうしても死角になりやすく、バイクや歩行者がいても気がつかないことがあります。
これが巻き込み事故につながるため、防衛運転として初めからリスクがあるものだと考え運転しなければいけません。
そこにいるものだと思えば、注意を払うことができるはずです。
意外と思っていたり自分が大丈夫だと思ったりすると、交通事故のリスクは跳ね上がります。
自分の車が急停車した時に後ろの車はどう考えるか考え直してみましょう。
急ブレーキを踏んで止まられると対応が間に合わないかもしれません。
その場合後ろの車が悪いと言えるでしょうか。
交通事故になることには何も変わりはありません。
後ろの車が車間距離をとっていたとしても、ある程度速度が出ていれば急停車されると間に合わないのです。
こうした事故を起こさないためにも急停車を避ければいいだけでしょう。
防衛運転の基本的な部分となるため、ドライバーとして理解しなければいけないのです。
交通事故を起こさない!防衛運転の意味
安全運転は大切

普段からハンドルを握るドライバーとして安全運転を心がけているでしょうか。
館林周辺でも、交通事故は後を絶ちません。
車社会であることも理由の一つですが、ドライバーとしての安全意識の問題もあるのが事実です。
走っている車を見ても安全運転を意識していないと感じる場面もあるでしょう。
どうやってみてもスピードを出し過ぎている車も見かけますし、暗くなってきているのにも関わらずライトをつけていない場合もあります。
右左折をするのに、内側に大きなスペースを空けて自転車が入っていることに気がつかないと言ったドライバーは後を絶ちません。
スーパーやショッピングセンターの駐車場から出るときにこのような光景を見かけるでしょう。
誰がどう見てもその運転は危険だというのがわかっていても、本人の意識と技術が足りないのです。
ドライバーの意識と技術が影響する

ドライバーの意識として防衛運転と呼ばれることがあります。
防衛運転とはドライバーが交通事故を回避するために行う運転方法で、非常に重要な意味がわかっているのです。
ハンドルを握る以上いつ加害者になるかわからないのが事実です。
そのため交通事故を防ごうと思う意識を持って運転しなければいけません。
これが防衛運転の基本的な考え方です。
交通事故の発生時に被害を最小限に食い止めるためにも重要な行動で、自分を守るだけではなく相手も守る考え方になります。
防衛運転はドライバーの内面的な要素だけではなく技術的な部分もあるのは事実です。
それを踏まえた上で理解を深めなければいけないでしょう。
当たり前のことが防衛運転につながる

事故を起こさないためには何が必要でしょうか。
自分の体調が優れているように管理することも必要です。
調子が悪い時には車を運転しなければ、事故を起こす可能性は下がります。
痛ましい事故がいくつも起きていますが、お酒を飲んだら運転しないというのも防衛運転の重要なポイントです。
違反であるという状況の前に、自分で判断がつかなくなるような状況で運転すること自体が問題なのに気がつかなければいけません。
防衛運転は天候にも左右されます。
雨の日には普段よりもさらにスピードを落とし注意しながら運転するのは当然の行動でしょう。
雪の日であれば3倍以上の制動距離が必要になることを理解していれば、スピードを出すことはありません。
危険だからです。
防衛運転とは当たり前のことの繰り返しなのが理解できるでしょう。
本当に自分ができているかどうか一度振り返ってみる必要があります。
もしも防衛運転に当たらないような状況であれば、ハンドルを握るドライバーとして改めて運転を考えていかなければいけません。
交通事故で多い高齢者や子供たち
高齢者や子供達を巻き込む交通事故

館林周辺でも非常に多い事故のパターンとして高齢者や子供を巻き込んだ例があるでしょう。
実際に運転していても怖い思いをすることがありますが、子供や高齢者はドライバーが予測しない動きをすることが出てきます。
行動が予測できないと交通事故を防ぐことも出来ません。
予測が重要なポイントになりますが、実際に65歳以上の高齢者の半数は交通事故で亡くなってしまうのです。
高齢者に集中していることも理解しておかなければいけません。
子供達の交通事故では登下校時が多い

子供たちの交通事故として多いのは登下校時です。
特に小さな小中学生が多くなるのは、ドライバーとしても予測ができない行動を取られるケースが出てきます。
実際に15歳以下の死傷者数は減少傾向にあるのです。
ここからもわかる通り、スクールゾーンなどに指定されているところでは子供たちが出てくると思って運転する必要があります。
少し広い道でも陰から子供たちが飛び出してくるかもしれないと思わなければいけません。
登下校時の時間にあたる時には、いないところから子供が出てくるかもしれないのです。
館林の周辺で見ても学校に近い場所では非常に危険性が高いと言えます。
細い道も多く、子供達がどこかに隠れているかもしれません。
元気に溢れた子供達は、道路も遊び場にしてしまいます。
車が来ていることに気がつかないかもしれません。
だからこそドライバー側が発見しなければいけないのです。
歩行中や自転車が圧倒的に多い

子供や高齢者が絡む交通事故のケースでは、歩行中や自転車に乗っている状況が多く見られます。
高齢者では特に歩行中の交通事故が多く、圧倒的な数になっているのです。
これは警察庁が公表しているデータでもはっきりしており、65歳以上の高齢者の交通事故の状況を見ると、半数以上は歩行中に起きています。
高齢者となると視界も狭くなり、体も思っているように動かないケースもあるでしょう。
危険だと思っていても反応できないケースもありますし、そもそも危険である状況を見逃すことも多いのです。
ドライバーとしては子供たちが高齢者がいるのが分かれば、どんな行動を起こしても避けられるだけのスペースを取る必要があります。
速度としてみてもいつでも止まれるような体制を作らなければいけません。
これらは子供や高齢者だからというだけではなく、ドライバーの安全意識としても重要なポイントです。
同時に子供達は高齢者に対しても車が来ていることを示す行動が必要になります。
暗がりになるような時間帯であれば早めにライトをつけてあげるだけでも違うことを忘れないようにしましょう。
ライトをつけないで運転することがかっこいいわけではありません。
社用車ではなくマイカーで交通事故?その責任はどこに
社用車ではなくマイカーを使って事故を起こす

館林の周辺でも通勤で車を使う人は非常に多くいるでしょう。
車社会とも言えるこの地域では、車が必要となるケースは多々あります。
車がなければ生活できないと言えるほど不便な地域もあるのは事実です。
その中で、マイカーを使用して事故を引き起こした時のことを想定してみる必要があるでしょう。
社員として通勤や業務でマイカーを利用する可能性は常に出てきます。
社用車ではなく自分の車であるというところが重要なポイントです。
業務として認められていないケース

基本的な考え方として、その会社がマイカーの使用を認めているかどうかからスタートしなければいけません。
仮にマイカーを業務使用することを禁止としている場合、交通事故が発生しても責任は個人で追うことになります。
これは会社側が禁止していることを社員が行なっているからです。
社員は業務規則や責任の範囲を安全管理者に確認する義務があり、もしも必要であれば対応する保険に加入しなければいけません。
会社が守ってくれると思っていては大きな間違いなのです。
自分で範囲を知らなかったこと自体が問題を大きくしてしまいます。
最も基本的な部分として、この状況は個人がマイカーに乗っていただけという状況になります。
業務として認められなくなっているのです。
業務として認められているケース

業務として認められている場合には、会社は運行供用者責任を負うことになります。
マイカーを使用していたとしても、社用車と同じ扱いになるのです。
これは運行の支配や運行の利益が会社に属していることを示しています。
加害者に故意または過失がなかった場合でも、運行供用者責任が発生し損害賠償責任が生まれるのです。
会社の業務として認められれば使用者責任もあると判断されます。
問題は会社がマイカーの使用をどこまで認めているかです。
この範囲がわからなければ、会社は全ての責任を負うわけではなくなります。
通勤にマイカーの使用を認めていても、日常業務では使ってはならないとしているケースがあるでしょう。
通常業務は社用車を使うとしているのにも関わらず、マイカーで移動すれば会社は責任を負いません。
仕事なのにも関わらずこのような不利益が発生するのです。
社員としてどのようなことが決められているのか理解していなかったことが大きな原因でしょう。
事故を起こした時に焦って調べても間に合いません。
事前に業務規則を確認しどのような責任が発生するのか理解してマイカーは使う必要があるのです。
楽だからと思ってマイカーを使って交通事故を起こせば、非常に重い責任が降ってくるかもしれません。