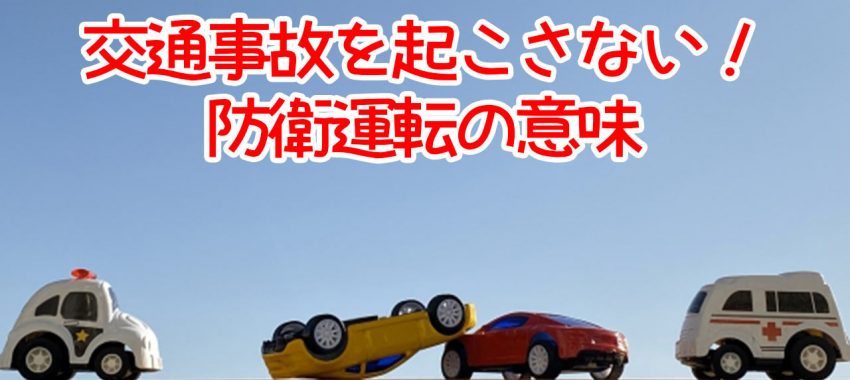交通事故予防
大雨で車が冠水したら
大雨が降ったら冠水する場所には近寄らない

館林も雨が降ると冠水しやすい場所がいくつもあります。
運転していると、大雨に遭遇する可能性がありますが、その時にどのような行動をとるのかが大きなカギを握るのです。
館林周辺の道路では、新宿のアンダーパスは冠水することでよく知られています。
他にも新しくできた道路ですが、東武鉄道のアンダーパス、ベルクの横にあるところも冠水しやすい傾向があるのです。
運転しているときにこのような場所に差し掛かったらどうなるでしょう。
冠水することが予想される場所には、大雨が降ったら近寄らないことが大切です。
水をかぶればエンジンが止まり動けなくなる

もしも、冠水したら、車から脱出する方法を考えなければいけません。
冠水した状態では、この後怪我では済まない状況が予想されます。
まず外側からかかる水圧によって扉は開かなくなります。
扉が開かないのですから脱出できないことになるのです。
簡単に開くと思うかもしれませんが、水圧も力は強く人間が落ち返せるようなものではありません。
さらにマフラーより高い位置まで水が来れば、エンジンの中に吸い込まれる可能性が出てきます。
マニュアル車であればクラッチを切った瞬間に水が浸入してきますし、オートマ車でも吸い込まれていく可能性があるのです。
仮に吸い込まれなかったとしても、エンジンの高さまで冠水すればバッテリーが耐えられません。
エンジンが止まれば現在の車は窓も開かない状態です。
脱出できなくなる可能性が更に高まります。
車は水位が車の底面まで来ると、押し上げる力が働きます。
路面から離れていくような感覚がしているのも、この力が働いているからです。
こうなるとエンジンがかかっていたとしても、車は動くことが出来ません。
できるだけ早く外へ出られる方法を考える必要があるのです。
ヘッドレストで窓を割る

扉が開かない状況であれば、エンジンが止まる前に窓を開けます。
力いっぱい押し下げることで、窓を開くことができるでしょう。
もしも、その前にバッテリーが止まってしまったら、シートにあるヘッドレストを抜き取ります。
現在のヘッドレストは2本の支柱で支えられており、抜き取ると先端部分が尖っていることがわかるでしょう。
車の窓ガラスは簡単に割れないように作られていますが、衝撃を点で与えることにより、破ることができるのです。
もちろん、割った時に怪我する可能性はありますが、これで脱出の経路が確保できるのは覚えておくべきでしょう。
一番大事なことは、冠水する場所には近寄らないことです。
興味本位で車を乗り入れた瞬間に、浮き上がってしまい身動きが取れないことも考えられます。
気がついたときには手遅れとなるため、大雨が降ったら注意して走りましょう。
左折で左側を開ける運転は危険です
左側を空ける大きなリスク

館林のスーパーなどで見かけることがある危険な行動として、左折するのに左側を空けている人を見かけませんか。
実は非常に安全意識の低い運転であり、防衛運転としても大きな問題を抱えています。
左折する際には巻き込みの危険性があるのは誰でも分かるはずです。
これがわからないドライバーはそもそも適性に問題があると言えます。
なぜ左側を開けてはいけないのでしょうか。
もしここに隙間があることに気がついた自転車がいて、そこを通り抜けようと思ったら危険だと思いませんか。
その自転車に気付かず車が左折すれば巻き込んでしまいます。
この隙間が空いていなければ自転車はその意識を持ちません。
歩行者も同じです。
教習所でも左折させてる時には左側にスペースを空けないと習うでしょう。
なぜならば隙間があれば入ってこようと考えるからです。
この危険予測ができていないからこそ、スーパーの出入口などで左側が空いています。
このような安全意識に対するレベルの低さは危機管理能力の低さとも言えるでしょう。
ハンドルを握る以上防衛運転は絶対に必要です。
その知識を持たないだけでも危険な状態にあることに気がつかなければいけません。
大回りしなければ曲がれない勘違い

左側を開けている理由の一つに、大回りしなければ曲がれないと勘違いしているドライバーがいます。
トラックが左側を開けて大回りをするのを見て、自分の車もそうしたら楽ではないかと考えるところから始まっているのです。
しかし、そもそも車の条件が違います。
トラックなどをホイールベースの長い車は、内輪差が大きくなります。
この内輪差をカバーするためには大回りしなければいけません。
車の前方部をできるだけ前に出してからハンドルをゆっくり行って曲がっていくのです。
一般の乗用車でこの動作が必要かと言われれば、ほぼ必要ありません。
一般の乗用車は最小回転半径が小さく、ホイールベースもトラックに比べれば遥かに短い車です。
このような車が大回りして曲がる必要性はほぼありません。

大回りして曲がるということはそれだけハンドルを切らなければいけません。
ハンドルを切る量が多くなればそれだけ注意が向いてしまいます。
何かあった時に停める動作も必要です。
つまり、それだけ危険があった時に対処できなくなるのです。
この状況を理解しているドライバーがどれほどいるでしょうか。
実際に大回りしているドライバーにはこのような危険意識はありません。
自分が曲がるのに楽ができると勘違いしているだけで、非常に危険な行動なのを理解していないのです。
大回りすればそれだけ視界も失われやすくなります。
みなければ安全とは言えない情報も増えていくのです。
それだけ運転も難しくなることを理解すれば、出口で左折しなければいけない時にどのような運転にするべきなのかすぐに分かるでしょう。
これがわからないドライバーは防衛運転ができない人であり、免許を返納するべきと言われても致し方ないレベルなのです。
強い方かもしれませんが、車は人と接触すれば怪我をさせてしまいます。
大きな交通事故につながる前に運転を理解し直す努力が必要です。
安全運転は確認からの情報が必須
車を安全に運転することと確認

車の運転で大切なことは何かと言われれば、安全の確認以上のことはありません。
自分が安全であるかどうか確認し、安全な運転を心がけることにより、交通事故の可能性を下げられます。
もちろん全てゼロになるとは限りません。
ですが少しでも安全な運転を心がけるためには、確認という行動が欠かせないのです。
なぜ確認が必要なのか改めて考えてみる必要があるでしょう。
情報がすべて

我々が車を運転するときに大切なことは情報を得ることです。
今目の前に車が走っているかどうか、対向車が来るかどうかは全て情報です。
歩行者が見えていたりすることもあるでしょう。
もしかしたら止まっている車が目の前にあり、その陰に子供がいる気配がするかもしれません。
これも全て情報なのです。
仮にこの情報がなかったと仮定しましょう。
対向車が来るかどうかわからないところで車線をはみ出して走ったらどうなるか、ドライバーであればすぐに分かるはずです。
かわすことができなければ正面衝突する交通事故になります。
歩行者がいることに気がつかず左折したらどうなるでしょうか。
その歩行者を巻き込み人身事故を起こす可能性が高いはずです。
目の前の車が急ブレーキを踏んだことに気がつかなければ追突するかもしれません。
全ては状況がわかれば回避できる部分があります。
どれもすべて情報が大切になるのです。
状況を判断するためには全て情報から判別していかなければいけないのが車の運転なのを忘れてはいけません。
確認をする行動の意味

情報を得るためには確認が必要です。
例えばバックミラーやサイドミラー、アンダーミラーなどを見て問題がないか確認する行動はドライバーなら必ずします。
前を見て運転するだけではありません。
自分の左右や後ろに何か問題があるかどうか、他の情報も加味しながら運転するのです。
つまり確認ができている人ほど安全な運転に近づくと言えるでしょう。
逆に情報を得られない人は常に危険と隣り合わせになります。
それがドライバーだけであれば構いません。
自己責任になるからです。
ところが交通事故には、他の人を巻き込む可能性が出てきます。
自分だけでは済まないのです。
初心者の若葉マークであろうとも、路上に出れば一人のドライバーとして同じ扱いになります。
交通事故を起こした時に初心者だから許されることはありません。
経験が少ないから人をひいても許されることなどありえる話ではないでしょう。
だからこそ常に安全かどうか確認し運転しなければいけません。
いかに安全かどうか確認できる癖をつけることが、どんなドライバーにでも求められる条件になるのです。
忘れてはいけません。
事故を起こせば様々な人の運命を狂わせます。
自分の運命を狂わせるだけではなく、被害者の運命も変わってしまう状況を理解して運転しましょう。
防衛運転の鉄則とは
ドライバーが持たなければいけない防衛運転

防衛運転を心がけている人は非常に多くなってきました。
本来言葉にしないでも、ドライバーが意識していかなければいけない部分です。
その防衛運転の中には心がけなければいけない鉄則がいくつもあります。
改めて自分が守れているかどうか、これから先も心がけなければいけない部分として認識し直す必要があるでしょう。
子供はバスやタクシーなどの影からは飛び出してくると考える

防衛運転では子供に注意するのが最初のポイントです。
子供は大人が想像している行動とは異なる場合がよくあります。
車がきているのに飛び出す可能性があるのもその行動の一つでしょう。
常に子供が飛び出すかもしれないという考えを持てば、安全運転に繋がるのは確かです。
道路に親子を見つけた時には、速度を落とし徐行するのが基本です。
特に道路を挟んで両側にいるのを見かけた時には子供が親の方向へ飛び出すかもしれません。
もちろん、子供が危険だと考えていればこのような行動は起こしませんが、車がいることを視野に入れていない可能性もあるのです。
飛び出すかもしれないと分かっていればこちらも準備ができます。
ブレーキも組めるようにしながら、すぐに停車できる速度に落とすことが防衛運転として大切です。
バスやタクシーが停車している時も危険があると考えなければいけません。
利用者はそれらの交通機関から降りてくるのです。
危険があると思って降りる人もいますが、車に気がつかない場合もあるでしょう。
交通事故に繋がる非常に危険な状況となるため、防衛運転が必要となるのです。
ドライバーとしての注意も大切

自転車を見かけた時にも注意が必要です。
自転車が急に曲がるかもしれませんし、倒れてくるかもしれません。
高齢者の方が突然飛び降りて止まってしまう状況を見たことがあるでしょう。
速度を落としてすれ違うと思っていたのに、突然飛び降りられてしまうと減速が間に合わない可能性もあるのです。
自転車は危険なものだと考え感覚を取って走ることが防衛運転につながります。
左折時には巻き込み事故を起こさないように注意します。
日本の車は右ハンドルが基本で左側通行です。
左側はどうしても死角になりやすく、バイクや歩行者がいても気がつかないことがあります。
これが巻き込み事故につながるため、防衛運転として初めからリスクがあるものだと考え運転しなければいけません。
そこにいるものだと思えば、注意を払うことができるはずです。
意外と思っていたり自分が大丈夫だと思ったりすると、交通事故のリスクは跳ね上がります。
自分の車が急停車した時に後ろの車はどう考えるか考え直してみましょう。
急ブレーキを踏んで止まられると対応が間に合わないかもしれません。
その場合後ろの車が悪いと言えるでしょうか。
交通事故になることには何も変わりはありません。
後ろの車が車間距離をとっていたとしても、ある程度速度が出ていれば急停車されると間に合わないのです。
こうした事故を起こさないためにも急停車を避ければいいだけでしょう。
防衛運転の基本的な部分となるため、ドライバーとして理解しなければいけないのです。
交通事故を起こさない!防衛運転の意味
安全運転は大切

普段からハンドルを握るドライバーとして安全運転を心がけているでしょうか。
館林周辺でも、交通事故は後を絶ちません。
車社会であることも理由の一つですが、ドライバーとしての安全意識の問題もあるのが事実です。
走っている車を見ても安全運転を意識していないと感じる場面もあるでしょう。
どうやってみてもスピードを出し過ぎている車も見かけますし、暗くなってきているのにも関わらずライトをつけていない場合もあります。
右左折をするのに、内側に大きなスペースを空けて自転車が入っていることに気がつかないと言ったドライバーは後を絶ちません。
スーパーやショッピングセンターの駐車場から出るときにこのような光景を見かけるでしょう。
誰がどう見てもその運転は危険だというのがわかっていても、本人の意識と技術が足りないのです。
ドライバーの意識と技術が影響する

ドライバーの意識として防衛運転と呼ばれることがあります。
防衛運転とはドライバーが交通事故を回避するために行う運転方法で、非常に重要な意味がわかっているのです。
ハンドルを握る以上いつ加害者になるかわからないのが事実です。
そのため交通事故を防ごうと思う意識を持って運転しなければいけません。
これが防衛運転の基本的な考え方です。
交通事故の発生時に被害を最小限に食い止めるためにも重要な行動で、自分を守るだけではなく相手も守る考え方になります。
防衛運転はドライバーの内面的な要素だけではなく技術的な部分もあるのは事実です。
それを踏まえた上で理解を深めなければいけないでしょう。
当たり前のことが防衛運転につながる

事故を起こさないためには何が必要でしょうか。
自分の体調が優れているように管理することも必要です。
調子が悪い時には車を運転しなければ、事故を起こす可能性は下がります。
痛ましい事故がいくつも起きていますが、お酒を飲んだら運転しないというのも防衛運転の重要なポイントです。
違反であるという状況の前に、自分で判断がつかなくなるような状況で運転すること自体が問題なのに気がつかなければいけません。
防衛運転は天候にも左右されます。
雨の日には普段よりもさらにスピードを落とし注意しながら運転するのは当然の行動でしょう。
雪の日であれば3倍以上の制動距離が必要になることを理解していれば、スピードを出すことはありません。
危険だからです。
防衛運転とは当たり前のことの繰り返しなのが理解できるでしょう。
本当に自分ができているかどうか一度振り返ってみる必要があります。
もしも防衛運転に当たらないような状況であれば、ハンドルを握るドライバーとして改めて運転を考えていかなければいけません。
交通事故で多い高齢者や子供たち
高齢者や子供達を巻き込む交通事故

館林周辺でも非常に多い事故のパターンとして高齢者や子供を巻き込んだ例があるでしょう。
実際に運転していても怖い思いをすることがありますが、子供や高齢者はドライバーが予測しない動きをすることが出てきます。
行動が予測できないと交通事故を防ぐことも出来ません。
予測が重要なポイントになりますが、実際に65歳以上の高齢者の半数は交通事故で亡くなってしまうのです。
高齢者に集中していることも理解しておかなければいけません。
子供達の交通事故では登下校時が多い

子供たちの交通事故として多いのは登下校時です。
特に小さな小中学生が多くなるのは、ドライバーとしても予測ができない行動を取られるケースが出てきます。
実際に15歳以下の死傷者数は減少傾向にあるのです。
ここからもわかる通り、スクールゾーンなどに指定されているところでは子供たちが出てくると思って運転する必要があります。
少し広い道でも陰から子供たちが飛び出してくるかもしれないと思わなければいけません。
登下校時の時間にあたる時には、いないところから子供が出てくるかもしれないのです。
館林の周辺で見ても学校に近い場所では非常に危険性が高いと言えます。
細い道も多く、子供達がどこかに隠れているかもしれません。
元気に溢れた子供達は、道路も遊び場にしてしまいます。
車が来ていることに気がつかないかもしれません。
だからこそドライバー側が発見しなければいけないのです。
歩行中や自転車が圧倒的に多い

子供や高齢者が絡む交通事故のケースでは、歩行中や自転車に乗っている状況が多く見られます。
高齢者では特に歩行中の交通事故が多く、圧倒的な数になっているのです。
これは警察庁が公表しているデータでもはっきりしており、65歳以上の高齢者の交通事故の状況を見ると、半数以上は歩行中に起きています。
高齢者となると視界も狭くなり、体も思っているように動かないケースもあるでしょう。
危険だと思っていても反応できないケースもありますし、そもそも危険である状況を見逃すことも多いのです。
ドライバーとしては子供たちが高齢者がいるのが分かれば、どんな行動を起こしても避けられるだけのスペースを取る必要があります。
速度としてみてもいつでも止まれるような体制を作らなければいけません。
これらは子供や高齢者だからというだけではなく、ドライバーの安全意識としても重要なポイントです。
同時に子供達は高齢者に対しても車が来ていることを示す行動が必要になります。
暗がりになるような時間帯であれば早めにライトをつけてあげるだけでも違うことを忘れないようにしましょう。
ライトをつけないで運転することがかっこいいわけではありません。
背の低い子どもたちの危険性と交通事故
背の低い子どもたちの危険

子どもたちと大人の違いは年齢だけではありません。
交通事故と関係性を見るときに大事なポイントは、子供たちは身長が低いという事実です。
車の運転でわき見運転が怖いのはなぜでしょうか。
それは、自分が危険性を見逃してしまう可能性が高いからです。
人間は危険だと思えば、それに対応する行動をします。
ドライバーとして危険予測しながら行動に移せないなら、免許証を返上したほうが安全です。
それほど危険予測は重要な意味を持ちます。
その点で子どもたちは大人よりも背が低く、見逃してしまう可能性があるのです。
現在の自動車事情を考えてみましょう。
以前はセダンタイプの車高の低い車が多くみられました。
これは館林など北関東でも変わりません。
現在はミニバンなど車高が高く、車自体も大型化しています。
その分、背の低い存在は見逃しやすくなってきているのです。
これを死角呼びます。
全く見えない位置が生まれるのが資格で、ボディの影などに入ると見えないこともあるでしょう。
ミラーなどで死角を補うように作られてきましたが、これも完全ではありません。
車の多いところで危険は隠れている

ショッピングモールなどでも気を付けなければいけません。
館林周辺にもいくつもありますが、こうした場所では車が多数止めてあります。
車が密集しているところでは、子どもたちの姿がはっきり分かりません。
車の陰に隠れているケースもありますし、背の低い子どもたちが四角に入り見えないことも多いのです。
最近のミニバンなどは、バックする時カメラで見れるようになっています。
このカメラは万能ではありません。
それどころか後方しか視界に入らない可能性も出てきます。
カメラに頼っていると、横から出てくる子どもたちを見逃す可能性が高いのです。
特にカメラは下を向かなければ見えない位置についています。
左右のミラーを見ないでバックすることが多いでしょう。
ちゃんと見ているとしても、カメラの映像を見る時に目を離すのです。
危険予測は情報を有効に生かさなければいけないため、十分注意しなければいけません。
予測しにくい子どもたち

子どもたちの動きは予測できないことができます。
普段から予測できる人はほとんどいないでしょう。
子どもたちの運転する自転車を想像してみてください。
バランスをとるためにフラフラと左右に動いたとします。
この動きの予測ができるかと言われれば、ほとんどの人はできません。
動くだけではなく突然転んでしまうかもしれませんし、自転車だけ投げ出す可能性もあります。
このような危険の予測もドライバはしなければいけないのです。
それだけ子どもたちの行動は、注視しておく必要があるでしょう。
最近ではペダルを外した自転車で、子どもたちが車道で出てくるケースもあります。
この自転車は実は遊具であり公道で使用することは禁止されています。
このような危険まで存在する以上、背が小さく認識しにくい子どもたちの特性も理解し、安全確認をしていかなければいけません。
スタンディングウェーブ現象とは
タイヤが波立ちパンクするスタンディングウェーブ現象

車を運転するなら、常にタイヤの空気圧には注意しなければいけません。
もし、タイヤの空気圧が不足するとどうなるか、考えたことはあるでしょうか。
タイヤは空気が入っている状態で機能するように作られています。
この空気が不足することで、本来起こらない現象が起こるのです。
それがスタンディングウェーブ現象であり、誰でも起こる可能性があります。
スタンディングウェーブ現象が起こる原因

タイヤは高速走行すると、接地面から後方に力が掛かります。
この時に波状に変形してしまうのが、スタンディングウェーブ現象です。
タイヤはゴムでできており、歪みにも耐えられますが、あまりに複雑な波がタイヤにかかると破断してしまう可能性があるのです。
1つの波なら問題ありませんが、ゴムの伝達速度や回転速度によっては複数重なってしまいます。
タイヤの温度も急激に上昇してしまう恐ろしい状態です。
一番の問題は、タイヤの空気圧で、回転速度が上がるとどんどんとゆがみが出てきます。
歪みも戻ろうとする力が掛かりますが、戻る前に回転してしまうのです。
この力がどんどんと重なるのが問題ですが、適正空気圧であれば問題ありません。
しかし、タイヤにかかる力はこれだけではなく、過積載など耐えきれないほどの重さが掛かっているときもスタンディングウェーブ現象が発生する可能性が高まります。
運転していても気が付きにくいのがスタンディングウェーブ現象で、突然ハンドルを取られたり、操作不能に陥ったりします。
タイヤが破断しバーストすれば、そのまま大きな交通事故につながるケースも出てくるのです。
スタンディングウェーブ現象を防ぐため

スタンディングウェーブ現象の対策は、タイヤの空気圧を適正に保つところからスタートしなければいけません。
空気圧が低くなると、その分ゆがみが出やすくなるからです。
これは車の種類やタイヤによっても異なるため、正確に確認が必要でしょう。
過積載を防ぐことも必要です。
積載重量を超えると、タイヤにかかる負担が変わります。
重いものを載せれば、当然タイヤに負担が増えるからです。
同じ空気圧でも積載重量が増えれば、タイヤにかかる負担も増大するからです。
タイヤの質も考えなければいけません。
スタッドレスタイヤなどは柔らかい材質が使われていますが、その分ゆがみやすい特徴も持っているからです。
高速走行もスタンディングウェーブ現象につながるため、必要以上に速度を上げて運転しないことも大切になってきます。
常に点検して安全に運転することが求められますが、意識の部分でこういった危険があることを理解しておかなければいけません。
知識があれば、どれだけ危険ナノかも理解できるからです。
交通事故の知識
交通事故にあったらどうするのか

自分が交通事故にあったらどう考えた時、どのような行動をするのか考えてみなければいけません。
自分が加害者であるだけではなく、被害者の時にもどのような行動をとるべきか考えてみる必要があるでしょう。
それが自分を守るために必要となるからです。
実際の交通事故や巻き込まれた時にどうなるのかを知らなければ、怖さはよく分かりません。
なぜ危険なのかどのようなことをしたら危ないのかを知らなければ、危険な状況を避けられなくなるでしょう。
それが交通事故であった時に、どのような被害を及ぼすのか、誰もが考えて見る必要があるのです。
パニックになったりする前に

交通事故の情報を提示していくのは、守らなければいけない状況があるからです。
自分の体や財産だけではありません。
誰かを巻き込んでしまえば、大きな損害が発生します。
その時に後悔しても間に合いません。
後悔先に立たずと思ったところで、その時には大きな被害が出てしまうからです。
交通事故を起こした時に、どのような行動をとらなければいけないのか理解しているでしょうか。
何を先にしなければいけないのか、その順番が頭になければパニックになるかもしれません。
パニックになっている時間の間にも、事故の状況はどんどん悪くなっていきます。
その行動の遅れが、後に大きな影響を及ぼせば、後悔しても後悔しきれなくなるかもしれないのです。
知っていそうで知らないことも出てきます。
警察へ届ける時の方法なども知らなければ、時間もかかってしまうでしょう。
それが自分にとってマイナスに変わるかもしれません。
保険会社への対応も同じです。
必要な交通事故の知識

交通事故で受けた怪我に関しても変わりません。
どのような怪我が起こるのか、その怖さを知っていますか。
むち打ち症がどのような症状を起こし、どれだけ苦しむのかわかっている人は、自分でなったことがあるか目の前で見ているかどちらかでしょう。
それほど怪我に対する知識は、あまり知られていないのも現状です。
知ることはとても大切です。
知識があれば、どのような事なのか理解できるようになるでしょう。
知らなければ、怖さもわからず、交通事故に対する認識も甘くなるからです。
交通事故の知識には多くのことが含まれています。
自分が 交通事故に巻き込まれた時にも、交通事故を起こしてしまった時にも役立つ情報が詰まっているのです。
車を運転する人だけではなく、普段の生活の中で交通事故に遭う可能性はゼロではない以上、皆さんが身につけておくべき知識と言えます。